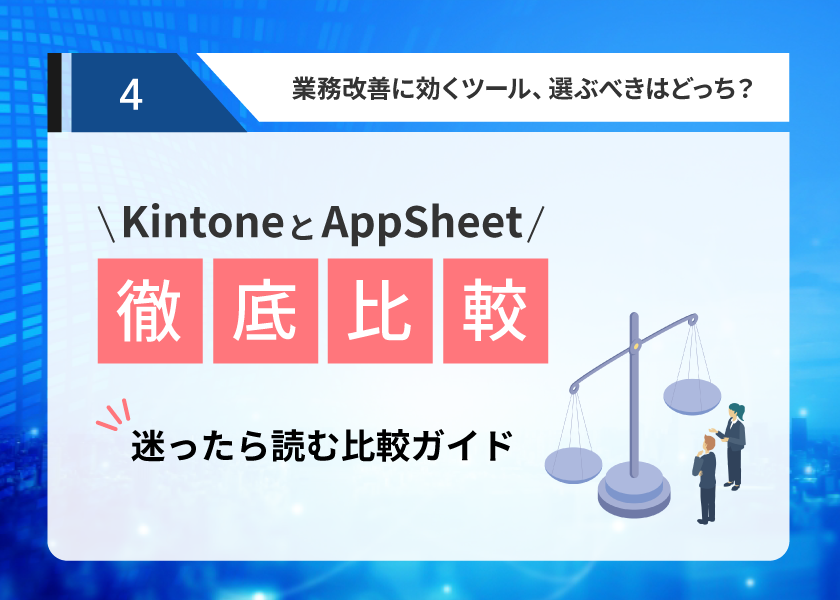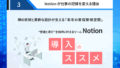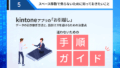【徹底比較】kintoneとAppSheet、どちらを選ぶべき?
業務改善の第一歩として、Excelや紙の管理から卒業し、「ノーコードツール」で業務アプリを自作したいと考えている方も多いのではないでしょうか。
そんな中で候補に挙がるのが、Kintone(キントーン)とAppSheet(アップシート)です。
どちらも人気のあるツールですが、特徴や得意な領域は大きく異なります。

この記事では、これから業務改善に取り組みたい方へ向けて、「KintoneとAppSheetの違い」について、やさしく・わかりやすくお伝えします。
1. kintoneとAppSheetの基本的な違いとは?

まずは、「そもそも何が違うのか?」をシンプルに把握しておきましょう。
以下の表に両者の違いをまとめました。
| 項目 | Kintone | AppSheet |
| 提供会社 | サイボウズ(日本) | Google(米国) |
| 主な対象 | ノーコードで業務アプリを作りたい日本企業 | Google Workspaceユーザー、予算を抑えたい企業 |
| 価格帯 | 月額課金+プラグインなどで追加費用が発生 | 無料枠あり。Google Workspace連携なら追加費用なしで使えるケースも |
| 特徴 | コメント機能、直感的な操作性、国産サポートの充実 | 自由な画面設計、帳票出力、外部データ統合が柔軟 |
| 操作難易度 | 初心者向け(直感的) | 中・上級者向け(設計自由度が高い分、難易度も高い) |
たとえるなら…
- kintoneは、「初心者向けのカスタマイズ可能な日記帳」のようなものです。
表にデータを入れ、コメントを書いて、社内で共有するまでがとても簡単に行えます。 - 一方で、AppSheetは「自由設計のツールボックス」です。
用途に応じてフォーム、一覧、帳票、外部連携などを自在に組み合わせられますが、その分だけ「設計する力」も求められます。
2. なぜAppSheetをおすすめしたいのか?

それは、以下の3つの強みがあるからです。
自由な画面設計ができる
AppSheetは、フォームのレイアウトや一覧画面の見せ方、ユーザーごとの表示切り替えなど、細部まで自分好みに設計できます。
たとえば、営業スタッフには訪問先リスト、工事担当者にはチェックリストと写真アップロード画面を見せる、といった役割に応じた画面の切り替えも簡単にできます。
帳票出力が標準でできる
Kintoneでは帳票出力に別売プラグインを導入する必要がありますが、AppSheetは見積書や報告書などのPDF出力を標準機能として搭載しています。
「え、これも有料なの?」という心配が少ないのが大きなメリットです。
Google Workspaceとの相性が抜群
すでにGmailやスプレッドシートを使っている企業であれば、AppSheetは非常にスムーズに導入できます。
「スプレッドシートがそのままデータベースになる」という手軽さは、Kintoneにはない魅力です。
3. AppSheetにも注意点があります
AppSheetは自由度が高い反面、「最初の設計」が難しく感じられるかもしれません。
はじめての方にとっては、「何から手を付けたらよいかわからない…」となりがちです。
ですので、ある程度ITに詳しい方が社内にいる場合や、外部に相談できるパートナーがいるとスムーズに導入できます。
4. Kintoneの強みとは?

AppSheetが“自由な設計”をウリにしているのに対して、Kintoneは「とにかく始めやすい」という点で多くの支持を集めています。
コメント機能が使いやすい
Kintoneにはレコードごとにコメントを書き込める機能があり、チームでの情報共有に便利です。
「報告書を提出したら、上司がその場でコメントを残せる」といった使い方ができます。
誰でも簡単にアプリが作れる
Kintoneでは、1つのテーブル(一覧表)がそのまま1つのアプリになるという設計になっており、操作も直感的。
Excel感覚で始められるので、ITが苦手な方でも扱いやすいのが特徴です。
5. 結局、どちらを選べばいいの?

どちらのツールにも魅力があり、どんな業務改善をしたいかによって適切な選択は変わります。
AppSheetが向いているのはこんな企業
- Google Workspaceを使っている
- ITリテラシーのある担当者がいる
- オリジナルなアプリを自由に設計したい
- コストを抑えつつ、PDF帳票などもしっかり出力したい
Kintoneが向いているのはこんな企業
- ノーコードツールを初めて導入する
- 日本語サポートが重要
- 情報共有やコメントを重視したい
- 複雑な業務ロジックはあまり必要ない
6. 最後に:業務改善は道具選びから
業務改善は、道具(ツール)選びがすべてではありませんが、成果を出せるかどうかを左右する重要な要素でもあります。

「本当に解決したい課題は何か?」
「現場の人が本当に使える設計になっているか?」
こうした視点で選ぶことが、失敗しないノーコード導入の第一歩です。